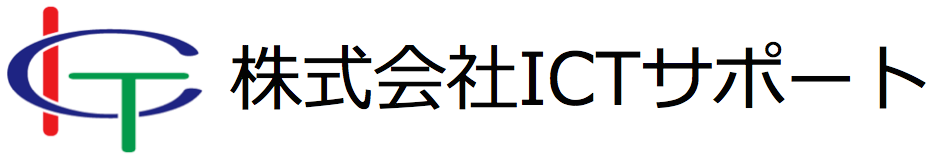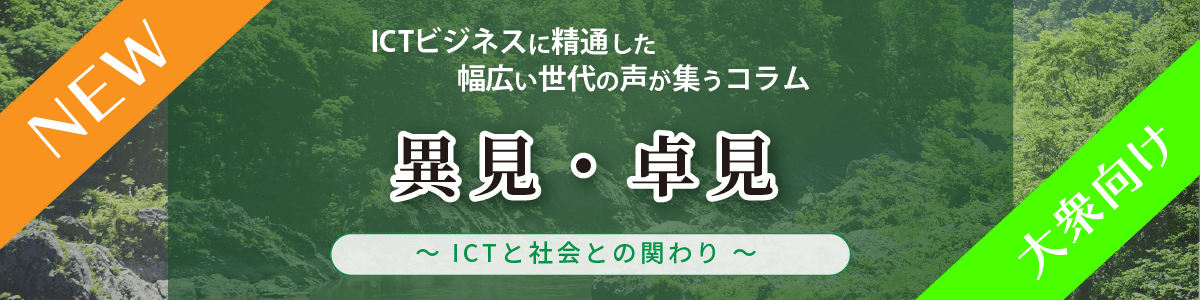<独立独歩な研究者 編>
小生、微力ながら雑誌の編集・取材を行っている。5W1Hを速報性で伝えることは、ネット社会に適しているようだ。しかし、情報の即時性に価値を求められることは、株式市場の上下動線の如く、ゼロイチの情報で、内容に深みが感じられない。世間の「筋金入りのモノ」は、それでは動かない。市場経済でも、実は私情が背景にあり、需要と供給曲線以上に、偶然と失敗と無駄と反省と歴史と欲望と胃袋と異性が潜んでいる。広報から発表するプレスリリースを右から左へ流すのは、どうやら新人記者に任せ、年齢を重ねてきて初めてわかる壁にどう向き合ってきたか、生きていくヒントとなるそのストーリーを文字として取材を続けることに、小生は、価値を感じる。昨今、失敗に陥り悪い状況でも、その変化を楽しむ余裕が無くなり、それをアドバンテージとして活用する智恵も会話もなくなり、スマホによる個別化社会は、実は危険なポピュリズムに似た付和雷同の如く奇妙なコモンセンスへ導くようだ。
地道にモノづくりを続けてきたシニアエンジニアは違う。リスペクトの神聖領域対象だ。制度、社会、体制、組織、人間関係が邪魔をしても、孤立し悪い環境下であっても、それを超える強さがある。これが、「研究」という最大結果かもしれない。
中華思想旺盛な知人の中国人でも、同じ東アジア地域の儒教文化圏所以か、日中両国関係が冷え込んでいても日本人のきめ細やかなモノづくりに対して、尊敬の念を持つ。出来上がった成果物をみて、彼らも感じるところがあるようだ。この国の「諦めない」という頑固さがカタチに現れた結果だろうか?それが、世界が認めるグローバリズムに勝負できる「ほんまもん」かもしれない。
周りの目を気にせず、信念のある独立独歩もシニアの特権だ。
<居酒屋主(あるじ) 編>
大学の通学路沿いにあり、都内JR駅にも近い「ある居酒屋」。家族代々営んでいるようで、小生、在学中からその名を記憶している。近距離にある他学部学生の御用達のようで、卒業後、数年経ってもいつでも寄れる帰省先のような存在だ。小生、今夏の盆休み前に、初めて、その店に訪れた。
店の主が、熱さを加減したおしぼりを客に手に届くような高さで、カウンター越しに手渡す。卒業生が立ち寄ったと言わんばかりしっかり目線を合わし慣れた対応。茶会の一期一会の如く、しかしながら肩肘張る必要のない実家に居る気分に導くよう緊張感を解かせる。そこに会話があったかどうか忘れたかが、主と客との居心地の良い関係の始まりだ。
その後は、娘かはたまた婿嫁の若女将が、注文に応じる。その主は、気がつくとカウンター内の椅子に腰かけている。そこからは、店のすべてが見える位置だ。こちらと言えば、自分のペースで酒を口にしながら、店内に流れるTV五輪番組に耳を傾けていく。
ひとつひとつが自然体。マニュアルではなく、相手に媚せず、初対面であっても両者の関係には、緊張感がない。しかも、店全体を俯瞰し、客の様子を伺いながら、息子夫婦(娘夫婦?)が行う段取りの過不足部分を丁寧に補う。それは、風景の一部のようにあくまでも無為自然の情景の如くだ。
年齢を重ねて、一線を退いても、重要な役割がある。息子が跡取りし店を引き継いでも、家族や孫の面倒をみながら、長年の常連の「お得意さん相手」という重責がある。それは、若輩者が首を突っ込める浅いものではない。かと言って、一見さんに対して粗相に対応することでもない。
シニアだからできる羨ましい人間関係作りの醍醐味だ。
<銀座のママ 編>
母校では、中退した方が社会で出世するという「伝説的なジンクス」がある。昨今、鬼籍に入られた「昭和の放送人」とよばれた大先輩もそうだ。当大学には、音楽学部があるわけでもなく、また医学部が存在するわけでもなく、なぜか多岐に亘り、各界最前線で有名となり、多くのOBがそれぞれの場で活躍している。中には、「銀座のママ」もいる。以前、「同窓のママによるOB勉強会(仮)」と評して、営業時間前にその禁断の地へ踏み込んだ。「銀座で飲む」という人間交差点を教授いただいた。そこでも、学校のカラーが色濃く出るようだ。慶應義塾大学や学習院大学卒業の客人は、店のママがそれとなく紹介をすると同じ同窓生として名刺の交換をするほどのほど良い関係があるようだ。(しかし、当同窓生は、どうやらそうでないらしい。)
来店者の中には、数十年に亘り長く通う「常連」がいるらしい。それは、出世と比例するファクターのようだ。店の敷居を跨ぐキッカケは、若い時に上司のお伴などのようで、その後、取引先のお客様とご一緒されたり、複数回の来店があるようだ。その常連客の様子を店の彼女たちは、接客業のプロとして、感じ、観察し、時間を経てもその振る舞いを覚えている。彼らは、お伴・お連れの客人と楽しむだけでなく、店の女性も華やかにさせ、しかもその上、他の客にも迷惑がかからない配慮があるという。その後、ある日突然、重責に就いて再度来店され、そのことが分かるのだと言う。出世するということは、多くの人から認められることで、唯我独尊ではなく、関係するすべての人への配慮とそこからの応援・支援があったからのようだ。人間関係を心地よくまとめることは、俯瞰して物事を進めていくために重要なことで、これは、人生経験豊富なシニアしかできない。大人になっても更なる大人の世界があるようだ。まだ、まだ学ぶこと多し。奥深い。
<おもてなし 編>
「おもてなし」が流行している。ウチとソトがある日本文化では、ウチを他人に見せることを憚る。「表が無し」で「おもてなし」のようだ。そこには、ウチまでみせる開放性、信頼性、日常性を魅せることでもある。ソトの人を村八分にするのではない。実は、かなり重い意味を持っている。
剣道や柔道などの武道、茶道や華道は、礼にはじまり礼に終わると言う。五輪の試合でもその「礼」ひとつが意味を持ち、目に焼きつくこともある。礼やお辞儀は、実は「頭を上げる時」が重要で、「見定め」という。その間の取り方で、主側に招かれているのか、委ねられているのか、受け入れられているのか、判断できる臨界点だと指摘する作法の賢者が言う。挨拶一つで、信頼関係の有無が判断されているのである。
ところで、こちらの予定など構わないで、やたらと怒っている、文句を言ってくる強引なシニアがいる。小生、両親は、既に他界しているため、怒る、喧嘩する相手はもういない。そのため、この強引さは時として、実は有り難く思うこともある。この関係に外交辞令如き挨拶などは無用。時として、盆や彼岸の理由ではなく、こちらからもこのシニアに突然の連絡をすることがある。予想通り、電話の向こうで、疾風怒濤の如く、ダイレクト直球の如く、また何か怒っている。これは、「表はなし」どころではない。
強引な言動、行動でも、それだけの自信がなければ人に接することはできない。時として、経験不足、智恵不足、人脈不足の若輩者を振り回してほしい。陥りやすい、気がつかない失態は、なるべく回避し、他人への障害も最小限にし、時間を生産性ある方向に集中し、最大活用したいものだ。
近いうちにまたラーメン食べに「そのシニア」を訪ねていきたい。帰りがけに、自宅の冷蔵庫にあった何かで使わなかった高くない赤ワインを台所の隅にあったまだレシートが入っているシワのあるスーパーの袋に入れて、実家の母がそうしたように、小生に渡してくれるのだろう。これこそ、「表はなし」のおもてなしだ。