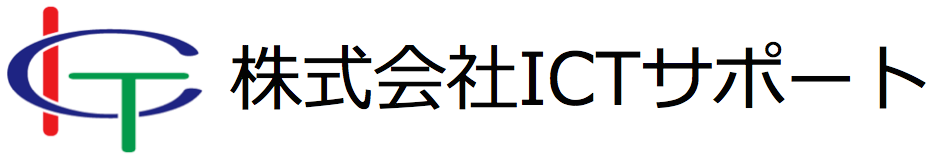西部劇はアメリカ映画の中で長く重要な歴史を持っている。ただ初期の西部劇は曲乗り、曲撃ちなど娯楽要素が主体の脇役的存在だった。ところがそれを一変させ、のちの西部劇のみならずアメリカ映画に大きな影響を与えたのが1923年、まだサイレント映画時代に制作された「幌馬車」(The Covered Wagon)である。パラマウント社が社運をかけて製作し国民的大ヒット作となった。ゴールドラッシュの前、東部アメリカから西部へ向かって新天地を求めて移動する人々の数千キロにわたる旅程を丁寧に描いている。100台を超える幌馬車が長い列を組んで進んでいく様はまさに記録映画を見るようだった。気候、水、食糧、先住民との闘い、内部の不和分裂など幾多の苦難に遭遇しながら進む様子は建国の歴史そのもので熱狂的支持を得たのも理解できる。その後西部劇はこの作品の成功により重要なジャンルへと成長していった。
数多くの西部劇がこれまで製作されてきた。開拓史をひも解くもの、華麗なガンファイトを見せるもの・・・と内容は様々だが女性が重要な役割をもって登場する作品は多い。熾烈な環境下で生きていく様々な女性群像は多くの作品で描かれてきたが、今回はその中で女性の意地とプライドを強く押し出している作品を語ろうと思う。対象となる西部劇作品は「女群西部へ」(Westward The Women)、「死の谷」(Corolado Territory)、「駅馬車」(Stagecoach)、の3作である。
1.「女群西部へ」(1951)
監督ウィリアム・ウェルマン、主演ロバート・テーラー。
西部で牧場経営に成功した牧場主が自分の牧場で働く100名のカウボーイの伴侶になってくれる女性を募集するためシカゴへ行く。3000キロの過酷な行程を覚悟して西部への移住を求め多数が応募したが、最終的に選ばれたのは138名、色んな能力や過去を持つ女性たちだった。移動中の死亡や離脱を考え最後に残るのは100人程度だろうというしたたかな読みもあった。この女性群と15名の護衛の男性がシカゴから西部へと大移動を行う行程、生活をつぶさに表現していく物語である。牧場主が同行を求める信頼すべきパートナーに選ばれるのがロバート・テーラーでおなじみの英国出身俳優、端整な二枚目だがこの映画ではひげを剃る間もなく女性たちを目的地へ無事に届けるために奔走する役柄である。
苛酷な行程が続き、馬車が動けない所は人力で引っ張り、急坂を滑り降りる馬車を全員が命がけで引き留める場面は印象的だ。靴の中は泥まみれ、衣服も裂け汗と油が染みつき、姿格好など構っておれない命がけの日々の連続で、ついていけない女性たちは引き返し、護衛のために選ばれた男も数人は女性と一緒に離れていった。
後半に入り、先住民との争いで牧場主を含む多数が死に、遂に男はロバート・テーラーともう一人になってしまう。万策尽きた感あり、「皆ここまでよくやった。明日から引き返す」と告げる。すると「Not me(私はいやよ!)」と一人が叫んだ。さらに「Not me」「Not me」「Not me」と疲労困憊しながらも目的地への進行を訴える女性の声が続く。その強い決意に動かされ続行を決意し、最後の難関、砂漠へ挑んでいく。
やっと砂漠を乗り越えた終盤、湖にたどり着き、女性たちが喜々として水と戯れるシーンは絵を観るような感慨があった。「目的地はもうすぐだ」と伝えられた女性たちはしかし「行きたくない」という。予想もしない反応、その真意は「男たちの前にこんな汚い姿で出たくない」という女性のプライドだった。「何でもいいから服や材料を持ってきて!」という女性の要望に応じ布集めに奔走するロバート・テーラーが牧場に先行し布をかき集める。やっと調達した布を選び奪い合う姿は壮観だった。
数日後粗末ながら急誂えの服をきちんと着て勢ぞろいし幌馬車に乗って静々とおすまし顔で現れたあの猛婦たちのいじらしい姿。困難を克服した女性たちには待ち受けた男性の中から好きな相手を選ぶ権利が与えられ、男たちは敬意をもって女性を迎えその選択を受け入れることを厳命された。新しいカップルが次々と並び祝福を受けるシーンは微笑ましい。
女性群を長期、長距離の大移動をさせるという奇抜な物語だがリアルな描写が全編を貫き印象に残る西部劇の佳作になっている。いったいこの物語の作者は誰・・・?と調べて納得した。あの「ある夜の出来事」(1934年)でオスカーを受賞し「スミス都へ行く」「素晴らしき哉、人生!」など名作を手がけた名監督フランク・キャプラ、だった。
2.「死の谷」(1949)
監督ラオール・ウォルシュ、主演ジョエル・マクリー、バージニア・メイヨ。列車強盗の前歴がある男、侠気があり信頼される。足を洗うつもりだったが恩人の依頼を断れず最後の列車強盗を決意する。この一味に加わる薄幸の混血女を演じるのがバージニア・メイヨ。口数は少ないが信頼できるこの男に底辺の者同士に通じるものを感じ強い愛情を抱く。最後の仕事を終えたら一緒になろうと考えた。
緻密に計画された列車強盗は成功し大金を手に入れたが仲間の裏切りで追われる身になっていく。列車強盗で得た大金をさびれた教会の修道士に託し献金箱に一旦隠し、分れて逃げようとするが男は傷つき峡谷に身を潜める。女は金の所在を教えることを条件に男を救出しようとするが容れられない。峡谷に向かって恋人の名を呼ぶ声が鋭く胸に迫った。
女はやっと男が潜む洞窟にたどり着いたが既に包囲の輪は狭まっていた。脱出も望めなくなった女には絶望的な意地しかなかった。女だてらに二挺拳銃を構え胸もはだけ形相すさまじく追手に向かって進んでいく。折角つかもうとした小さな幸せも望めなくなって薄幸の女は男の制止も振り切り拳銃を発射する。追手の銃撃に二人は手を重ねたままひとたまりもなく死んでいった。約20年後に登場するアメリカン・ニューシネマの傑作「俺たちに明日はない」のラストシーンを思い出させる凄絶なアウトロー二人の最後だった。西部劇ファンに語り継がれる伝説のシーンである。
きれいに再建された教会での修道士の言葉、「立派な若い夫婦が来られました・・・」大金は教会再建に使われていたのだ。ラストの平和な鐘の音が救いだった。
ラオール・ウォルシュは当時のトップ監督、バージニア・メイヨは自分を重用してくれる監督の期待に応えようと迫真の演技を見せており、その後この監督の作品のほか、米映画で活躍して行く。名匠ウィリアム・ワイラーの「我らの生涯最良の年」、ダニー・ケイと共演の「ヒット・パレード」などにも登場し古い映画ファンにはなじみの女優だが、数ある彼女の作品の中で演技の質が際立って高かったことを付記したい。
3.「駅馬車」(1939)
監督ジョン・フォード、主演ジョン・ウェイン、クレア・トレバー。西部劇の最高傑作としてだけでなくアメリカ映画の中でも異彩を放つこの映画はスピーディーで迫力あるアクションだけで語られる作品ではない。それぞれの人生を背負って登場する6名の乗客は1台の馬車に同席することになる。途中から乗り込む脱獄者・お尋ね者のリンゴー・キッド役はこの作品をきっかけに大俳優へ成長していく若き日のジョン・ウェインである。車中では協調と対立、相克が連続し、ここで織りなされる人間模様はこの映画の骨格をなしており単なるアクション映画ではない名作の魅力を放つ。
危険地域での駅馬車には通常騎兵隊の護衛がつくが、次の区間を騎兵隊の護衛なしで出発する事態になり、一行を率いる保安官が行くべきか留まるべきかを乗客の投票で決しようとする場面がある。「まずレディーの意見を聞こう」として乗客の1人、軍人の妻の意見を求めた。そのまま次の男性に聞こうとした保安官にお尋ね者のリンゴーが「もう一人のレディーには聞かないのか?」とたしなめる。乗客の1人である酒場女(クレア・トレバー)は一人前の扱いをされていなかったのである。「レディー」と呼ばれたのが自分であることに気付き驚いてリンゴーを見上げる女、女は生涯でただ一人自分を「レディー」と呼んでくれた男に心からの愛を感じた。リンゴーはこの駅馬車の目的地ローズバーグに住む三人兄弟に決闘を挑むためだけに脱獄した。三人はリンゴーの家族を殺害し裁判で不当な証言を行いリンゴーを投獄させていたのである。
女は町を追われるようにしてローズバーグ行きの駅馬車に乗ったのだがリンゴーの好意に底辺に生きる者同士に通じるものを感じ急速に愛を深めていった。二人は共に暮らそうと決意し、女は必死でリンゴーに勝ち目のない決闘を避けるように説き、仮に成功しても脱獄の上さらに殺人罪が加わり自分のために仇討をあきらめ国外へ逃亡するよう説得する。女の必死の願いにリンゴーは一旦その気になった。・・・しかし、先住民に既に包囲されつつあることを知った二人は一行とともに戦うことを決意する。
出発した駅馬車は待ち受けた先住民からの襲撃を受けた。攻防の末傷つき弾薬も尽き一行は死を覚悟する・・が間一髪の騎兵隊の応援で生き延び、目的地ローズバーグに到着した。女の懇願を振り切り、リンゴーは1対3の決闘に赴く。劇的に決闘を制し生き延びたリンゴーは自分を死ぬとあきらめていた女の前に現れた。二人の生活を始める前に法の裁きを受けるためである。二人は従容として法に従う決心をして保安官の用意した馬車に乗った。この映画の最後の見せどころ、リンゴーを逮捕、連行すべき保安官はおもむろにしゃがみこむ。道に落ちていた石ころを拾い、そのつぶてを馬の首に投げつけた。驚いた馬は立ち上がり一気に駆けだす。馬車は若い新しいカップルを載せ煌めくような未来に向かって走り去っていった。
<スクリーン憧子>